こんにちわ(‘ω’)ノゆとりPTです。
社会人として知っておくべき基本的な制度を解説します。
まず覚えておかなければならないのは、ケガや病気にかかった際に適用される公的保険です。
聞いたことはあるが、実際に何をどうすればよいか知らない人は多いはずです。
これが分かれば不要な保険に入っていたことに気づき、無駄な保険料を削減できるかもしれません。
そのためには「もしもの時に公的保険でどのくらいのお金がもらえるのか」を知っておくことが大切です。
今回は、3つの公的保険について分かりやすく解説していきます。
➀【労災保険】業務中のケガ・病気等
勤務中や通勤中にケガや業務が原因のうつ病などで休業しなければならなくなってしまった場合に適用されるのが「労災保険」です。
これは休業して4日目から支給される保険給付です。
金額は、平均給与額の80%(保険給付60% + 特別支給金20%)を受けられます。
なお、申請手続をして受理されてから給付決定されるまではおよそ1か月程度かかるのでご注意ください。
➁【傷病手当金】業務外のケガや病気
勤務外の時に病気やケガをして療養をするために休業する際には「傷病手当金」を受けられます。
これは一般の正社員の方なら毎月保険料を支払っている「健康保険」の制度が適用されるものです。
支給される金額は標準報酬月額の2/3で、最長で1年6か月受給できます。
仕事に復帰できた時点で支給終了です。
➂【高額療養費制度】手術を行なった場合
保険料を支払っている「健康保険」の制度が適用されるもので、医療機関や窓口で支払った金額が一定額を超えた際に支給される制度です。
先進医療などは該当しませんが、一般的な治療で大きな手術をした場合には、申請さえすれば後から差額が支給されます。
例:40歳、年収500万円、1か月の医療費が100万円の場合
たとえば、40歳で年収500万円の人の1か月の医療費が100万円だった場合、実際にいくら支払う必要があるのでしょうか?
正解は、高額療養費制度を利用するとおよそ8~9万円で済みます。
ただし、入院時の食事負担や差額ベッド代は含みません。
自己負担の上限額は年収や年齢によって異なり、その金額を超えた分が支給される仕組みです。
69歳以下の方の上限額一覧

注意点
これらの公的保険は、申請しないともらえないお金です。
該当していたにもかかわらず「知らないためにもらえない」といったことのないようにしっかりと理解しておきましょう。
まとめ
厚生労働省の「平成30年度 過労死等の労災補償状況」によれば、
「医療業」は「社会保険・社会福祉・介護事業」に次いで精神障害の多い業種となっています。
公的データを見ても、医療従事者のメンタルヘルスの不調は多いと言えます。
しかもその7割は看護職で休職に至るケースも多いです。
つまり、メンタルヘルスの不調により休職を余儀なくされた場合は、上記の3つの公的保険を利用し転職や復職の準備期間に当てましょう。
効率的に転職先を探すためにエージェントを利用しましょう。

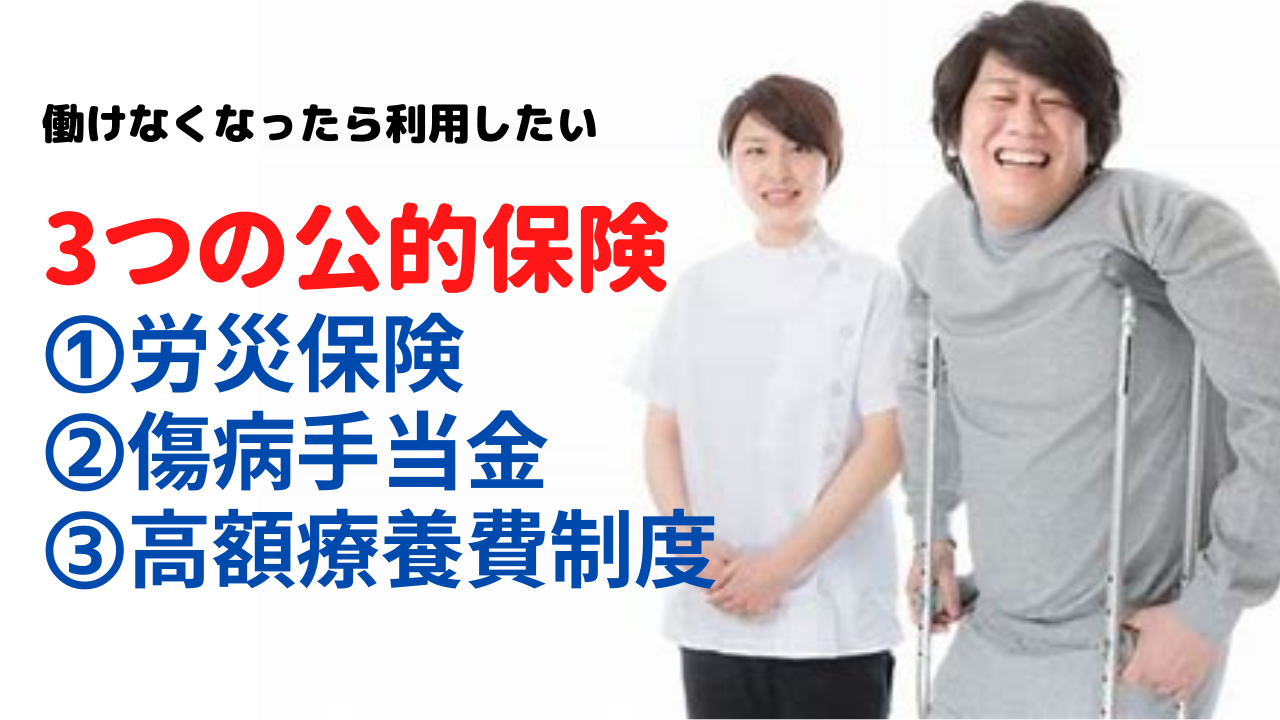





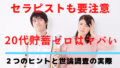
コメント