低年収である理学療法士は、結婚しても共働きは必須であると言えます。
年収400万円のセラピストでも共働きすることで世帯年収800万円は可能であり、やや裕福な分類に入れるとSNS上では見かけます。
2人以上の共働き世帯の年収は実際どうなのでしょうか?
今回は、全国の共働きの世帯年収と実際の生活について解説します。
共働きは必須?セラピストの世帯年収事情と現実を考える
世帯年収の平均は545.4万円
厚生労働省が2018年7月の世帯年収の調査では、世帯年収の平均は545.4万円となりました。
ちなみに、中央値は427万円となり、平均世帯年収以下の割合は61.5%です。
【参照元|厚生労働省「平成28年国民生活基礎調査概要」】
世帯主の年齢階級別でみると、
50歳~59歳の世帯年収が最も高く、最も低いのは29歳以下でした。
60歳以上の定年以降は、退職したり、勤務継続しても雇用形態などが変更しやすいため年収が下がります。
子育て世帯の実際の生活は苦しい
子育て世帯の世帯年収の平均は707.6万円と高い金額となりましたが、2017年より減少傾向にあります。
また、世帯構成別の生活意識に関しては、全体の6割弱が「苦しい」という回答をしています。
特に【子育て世帯(児童のいる世帯)】【シングルマザー(母子世帯)】が平均を上回る結果でした。
ただし、いずれも前回調査した2013年からは減っています。
【参照元|厚生労働省「平成28年国民生活基礎調査概要」】
貯蓄できていない世帯が多い
世帯主の年齢別に貯蓄の増減状況を調査した結果では、
前年と比較して「貯蓄が減った」と答える世帯が4割にのぼりました。
また世帯主が65歳以上になると、その約半数が貯蓄が減少したと回答しています。
貯蓄が減った理由をみると、どの年齢階級においても「日常生活費への支出」が6割を超え、
30歳~59歳にかけては「入学金、結婚費用、旅行等の一時的な支出」が3割強となりました。
子育て世帯の世帯年収平均が707.6万円と高く、生活に余裕があるように感じますが、
「生活が苦しい」と回答した割合が6割を超えていることからも、様々な費用や支出が重なり家計を圧迫していることがわかります。
【参照元|厚生労働省「平成28年国民生活基礎調査概要」】
共働き世帯の世帯年収別収支を比較!
共働き世帯の世帯年収を比較しましょう。
統計局が実施した家計調査報告によると、共働き世帯の世帯年収は694万円、手取りの収入は555万円でした。
世帯年収600万円の場合
新人セラピストの共働き世帯モデルです。
夫婦それぞれ300万円の収入とすると、手取り年収は約480万円になります。月額では約40万円です。
| 支出内訳項目 | 金額 |
| 生活費 | 約29.0万円 |
| 住居費 | 約6.0万円 |
| 合計 | 約35.0万円 |
【参照元|e-state】
世帯年収600万円の家庭の支出の合計金額は約35万円。
月額の収入は約40万ですので、約5万円が貯金にまわせる金額です。
統計データでは、約9.3万円の貯蓄額が平均のようです。
世帯年収700万円の場合
一般的なセラピストの共働きモデルと言えます。
夫婦それぞれが350万円の実収入の場合、手取り年収は約560万円になります。
月額では約47万円です。
子育て世帯の世帯年収平均は707.6万円でした。
また、世帯年収が600万の家庭とくらべ、貯金額は低く、住居費が増える傾向があります。
| 支出内訳項目 | 金額 |
| 生活費 | 約34.0万円 |
| 住居費 | 約7.0万円 |
| 合計 | 約41.0万円 |
【参照元|e-state】
支出の合計は41万円。月額収入から差し引いた貯蓄可能額は約6万円です。
統計データからの平均貯蓄額も約6万円です。
世帯年収800万円の場合
セラピストと一般職の夫婦モデルです。
夫婦それぞれ400万円の実収入の場合、手取り年収は約640万円になります。月額では約53万円です。
世帯年収700万円の過程とくらべ、生活費が高まる傾向にあります。
| 支出内訳項目 | 金額 |
| 生活費 | 約41.0万円 |
| 住居費 | 約6.5万円 |
| 合計 | 約47.5万円 |
【参照元|e-state】
世帯年収800万円の家庭における支出合計は、約47.5万円です。
月額の収入が53万円ですので、貯金に回せる金額の平均値は5.5万円となります。
貯金額の統計平均は9.7万円です。
世帯年収900万円の場合
中堅セラピストと看護師の夫婦のモデルです。
夫婦それぞれ450万円の実収入の場合、手取り年収は約716万円になります。
月額では約60万円です。
| 支出内訳項目 | 金額 |
| 生活費 | 約40.2万円 |
| 住居費 | 約7.4万円 |
| 合計 | 約47.6万円 |
【参照元|e-state】
世帯年収が900万円の家庭では、支出の合計は約47.6万円が平均でした。
月額の収入と差し引くと約12.4万円が貯金ができる金額です。
統計データでは、約10.1万円が平均の貯金額となっています。
世帯年収1000万の場合
50代の役職セラピストと50代キャリアウーマンのモデルです。
夫婦それぞれ500万円の実収入の場合、手取り年収は約800万円になります。月額では約67万円です。
| 支出内訳項目 | 金額 |
| 生活費 | 約47.0万円 |
| 住居費 | 約8.0万円 |
| 合計 | 約55.0万円 |
【参照元|e-state】
世帯年収1000万になると、支出の合計が約55万円と大きく跳ね上がります。
月額の収入から差し引くと、貯金できる金額は12万円です。
統計データの平均貯金額は、約15.8万円です。
これらの結果からわかること
➀共働きでも支出を抑えなければ生活は苦しい
世帯年収と貯金額は必ずしも比例せず、所得に応じて計画的に収支コントロールをすることが大切であると言えます。
収入が大きくなるにつれて生活のグレードを上げるのではなく、一定の生活基準を保つ方が重要となります。
➁出産・育児等で世帯年収が変動することを念頭に置く
女性においての一人当たりの年収は、
50歳~59歳の263.8万円が最も高く、最も低いのが30歳~39歳の177万円となりました。
これは、女性が結婚・出産・育児によって就業日数が減少するM字カーブの影響が出ていることを表します。
➂男性セラピストは自分の収入を最大化させることを目指すべき
出産・育児というどうしても女性に頼らざるを得ない場面が必ずあります。
そのため、共働きでも女性側の収入を想定して生活設計をすることにリスクがあります。
まずは、男性側がもしもの場合でも家計を支えられる程度は稼いでくることが大切です。
転職エージェントを使用することで年収UPを効率的に図れます。
➃計画的に住宅ローンを組んだり資産運用を行なう必要がある
世帯年収が高いからと言って、身の丈に合わない高額な住宅ローンを組むのは危険です。
男性と違い女性の年収は減少する可能性があるためです。
定年後もローンを払い終えない世帯も出てきています。
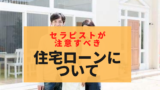
子どもの養育費や教育費は高額であり、老後資金と合わせてジュニアNISAや積立NISA・iDeCoを活用し計画的に運用を行ないましょう。


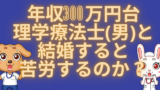

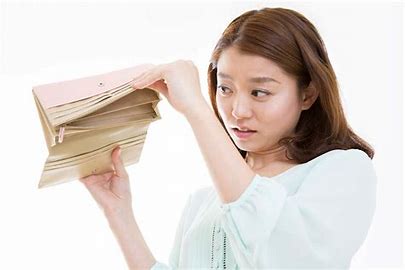




コメント